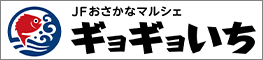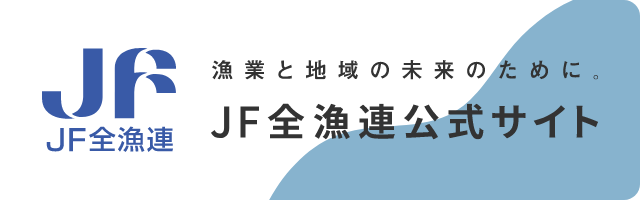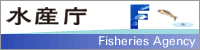浜プランの取組地区数
5
5
4
地区
※2023年3月末時点
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |