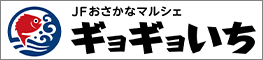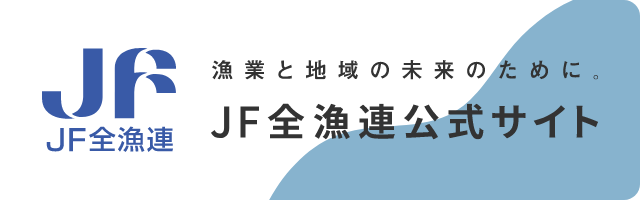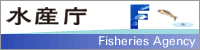浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
1.水産資源の安定と守り育てる取組
・枝幸さけ(193名)・ます(109名)定置網漁業者は、さけ・ますの河川への
遡上状況を確認しながら、遡上量が少ない場合などは休漁期設定や漁獲努力
量の削減(漁期期間中での揚網・早期切上)を行い、親魚の遡上量を確保す
る。また、宗谷管内さけ・ます増殖事業協会と枝幸漁協は、さけ・ますの孵
化施設や二次飼育池の改修、収容能力の拡大、海中飼育施設の網地を交換し
水質管理を徹底するとともに、各種調査や研修・勉強会を定期的に開催する
ことで、当該漁業者等は飼育技術、放流技術の普及を図り、健康で元気な稚
魚を育成する。
・ホタテガイけた網漁業者(233名)となまこけた網漁業者(19名)は、安定し
た資源の確保に向け下記の取組を行う。
・低気圧等に影響を受けない漁場を確立するため、ホタテガイ漁場のヒトデ駆
除や海洋モニタリングについても継続してデータを活用していく。更には周
辺海域の底質調査を実施し、未利用海域のうち生息条件を満たす海域の拡大
を図るとともに、稚貝放流を一定サイズ(3.5cm以上)とすることで、生存
率向上や漁獲サイズの大型化に努め、安定した漁獲量確保と向上を目指す。
・なまこけた網漁業者と枝幸漁協は、天然資源の増加につなげるため、平成29
年から水産普及指導所や関係機関と協力し、人口種苗放流(なまこ簡易採
苗)を試験的に実施している。また、枝幸港湾に設置されているなまこ礁に
放流することで、天然発生と種苗放流が調和した管理型漁業を目指すもので
あり、長年の資源調査と漁獲量の変動から資源動向を把握し、放流効果の判
定を調査する。
・枝幸採介藻漁業(うに108名・こんぶ85名)と枝幸漁協は、うに・こんぶの生
息環境を確保するため、水産環境整備事業による囲い礁を整備し、加えて水
深3m以深に生息する実入りの悪いうにの移植を実施し、適正な水深で餌料
のある漁場へ移植放流し資源増大に努める。
2.魚価単価向上と販路拡大への取組
・ホタテガイけた網漁業、さけ・ます定置網漁業、毛がにかご漁業、たこ漁
業、底建網漁業の各経営体と枝幸漁協は、衛生管理強化のため、屋根付き岸
壁での水揚げを徹底して行うとともに、取水施設の整備により消費者市場の
ニーズに応えるため、殺菌海水の使用や施氷の確実な実施に努めることで、
輸送中の鮮度保持と衛生管理による付加価値向上を図る。
・全漁業経営体及び枝幸漁協は、関係機関と連携し販売戦略を定め、秋さけ・
ホタテガイ・毛がにを中心に、その他の鮮魚貝類及び各種加工品について、
産地直販、販売促進イベントなどを通じて札幌や大都市圏で消費拡大を図
り、オホーツク枝幸産水産物を広く全国にPRすることにより枝幸地域全体の
販売額の向上に繋げる。
・GFPグローバル産地づくり推進事業を活用し、生産・加工等の体制構築を実施
する。また、東南アジアや米国を中心にホタテガイや輸出国のニーズによっ
て水産加工製品の輸出にも挑戦することで更なる輸出促進に向けた出荷体制
の確立と水産製品の付加価値向上を図る。
・枝幸漁協は、枝幸水産加工業協同組合、オホーツク枝幸ブランド推進本部
(枝幸町・観光協会)、枝幸町商工会関係者と連携して、「毛がに水揚げ日
本一」の町として知名度向上を図り、その知名度を生かして【枝幸ほたて】
のブランド化に取り組む。そのため、当組合のホームページを開設し高品質
な水産物や水産製品の魅力を強く発信する。また、地元漁業者が、食糧産
業・6次産業化交付金事業を活用してレストラン兼直売所を整備し、枝幸町
内で水揚げされた水産物を取り入れた料理の提供や特産品の営業をしている
ため、今後、第2・第3の漁業者兼経営者が出てくるよう関係機関と協議を
進める。
3.ホタテガイけた網漁業の乗組員確保対策
・枝幸漁協は、平成30年から令和7年までの間にホタテガイ採捕漁船建造を16隻
実施し、操業時の安全性向上と作業の効率化を図るほか、乗組員の給与や社
会保障など処遇改善に向け、他地区との比較協議を行う。また、枝幸漁協及
び枝幸町は、町外からの乗組員や漁業就業者を積極的に確保するため漁業就
業支援フェアへの参加や特定技能外国人制度利用のため、受け入れ体制の強
化及び宿舎の整備を行う。
・農山漁村振興交付金(渚泊)を利用し、都市部からの乗組員や新たな担い手
確保における研修や漁業体験を通し、枝幸地区の漁業の魅力をPRすることで
移住者、労働者を増やすため、漁業体験宿泊施設の建設について協議を進め
る。
4.水産物供給基盤の確保
・枝幸漁協は、漁業者の漁労作業の効率化及び共同化・協業化を推進していく
ため共同利用施設及び荷さばき施設等を整備する。
・枝幸漁協は、平成30年度に策定した【特定漁港漁場整備事業計画】に基づ
き、水産流通基盤整備事業の整備促進を要望し、陸揚げから出荷までの作業
動線の見直しによる適正化に加えて、衛生管理体制の構築による枝幸産水産
物のブランド化・輸出促進を図り、漁業収入の安定化、作業効率向上を目指
す。また、今後の増産体制や殻付きホタテガイの処理に備え、オートシェラ
ーの導入を検討し加工生産量の拡大による対EU・東南アジア・対米国向けの
輸出強化を図る。更には、水産物の鮮度保持に必要不可欠となる氷を製造、
保管・砕氷するための製氷機、貯氷庫、砕氷機、ホタテガイ等の出荷に必要
な大型トラックに対応するトラックスケールの順次整備を進める。加えて、
屋内専用の電動フォークリフト導入により、荷さばき所内の清潔保持・環境
保全に配慮する。
5.海業により漁業者の収入拡大
・整備予定の衛生管理型荷さばき所の活用及び製品開発部門と店舗を併設した
施設の整備により、魚価の付加価値向上を図る。
・枝幸町では、近年サケ・マス釣りが盛んになってきており、多くの釣り人が
訪れることで様々な課題が発生している。今後、課題解決に向け観光業と連
携したブルーツーリズムの推進を図り、「遊漁船業者登録」を取得した漁業
者は、漁協や枝幸町・枝幸町観光協会と協力し、秋サケ釣りフィッシング体
験や秋サケ加工体験等をしながら、秋サケ食文化の地域で受け継がれる漁師
料理等を通じ地域住民との交流を重視することで、枝幸町経済の活性化や事
業の多角化による所得の向上を図る。また、有識者や関係団体、漁港管理者
等の意見を踏まえ、漁港や海浜地の利用ルール、マナー確保対策、釣り人の
安全確保対策について検討する。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。