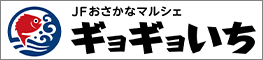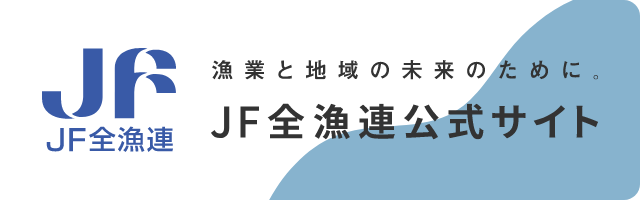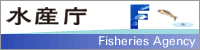浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
・刺網漁業者24経営体は及び漁協は、追直漁港周辺にてマツカワの種
苗放流を実施し、資源増大を図り、活魚出荷の拡大に努める。
・採介漁業者37経営体及び漁協は、うにの大型種苗(20mm以上)を20
万粒購入し直接放流することで資源の増大を図る。
また、高齢漁業者に優しい漁場を確保するべく、シルバー海域(年齢
70歳以上の漁業者のみが採取できる海域)を設定し、生涯にわたり漁
業が続けられる環境づくりに努めてきたが、高齢漁業者の所得維持・
向上を図るため、漁協は、共同漁業権管理委員会と協議のうえ、シル
バー海域の拡大に努める。
・室蘭海域において、かつてはこんぶ・わかめ資源が豊富で組合員のほ
とんどが採藻漁業に着業し、多くの水揚数量・金額があり組合水揚げ
の根幹をなしていた。しかし、近年の自然環境の変化などから採藻漁
場の荒廃・種の不着生・生育不足が顕著に現れていることから、採藻
漁業者26経営体及び漁協は、新規藻場造成及び現有藻場の改善のた
め雑海藻駆除を行い、安定的な海藻漁場を確保し、こんぶ・わかめの
資源増大と収入向上を図る。併せて、「ブルーカーボン事業」を推進
するべく、静穏海域においてこんぶ・わかめの種苗を購入後養殖・育
成し、さらにそれらから放出される胞子の成長を促進させる「うに殻
肥料」を設置することで、現状、磯焼けの危機にある藻場の回復・増
大に努める。また、滅菌海水設備や海水冷却装置・活魚水槽を備え
た、種苗を自家生産する施設の整備を検討する。
・ほたて貝養殖漁業者21経営体及び漁協は、ほたて貝の品質向上のた
め、老朽化しているほたて貝養殖施設の整備や、貝殻洗浄機の更新を
検討するとともに、市場や韓国等海外輸出用出荷時の風雨雪害による
ほたて貝の活力低下を防ぐべく、ほたて貝の水揚げ場の整備(岸壁防
風柵の整備を含む)の促進を開発局に要請する。
・また、ほたて成貝の生産を行う18経営体は、3年貝のうち殻径
13.0cm以上のものを「蘭扇」の名称で差別化し3年後の販売を目指
す。「蘭扇」の生産については、生産目標を設定し、稚貝分散の段階
から特化した生産方法を検討し、対象漁家で統一を図る。また、販売
方法については、消費者ニーズや相場を踏まえて抜本的に見直し、数
量限定や高級志向を強化する等、時代にあった販売戦略を立て、オン
ラインショップをメインとして販売することを検討する。
・また、8枚/kg~9枚/kgサイズの水産加工業者向けに出荷していた
2年貝が韓国からの要求サイズに合致することから、今後見込まれる
内販量を考慮しつつ、段階的に韓国等海外輸出用の2年貝の生産量増
大を図る。
・さらに、ほたて貝養殖漁業者21経営体の内、地撒き用ほたて稚貝の
生産・販売を行っている8経営体は、函館水産試験場及び胆振地区水
産技術普及指導所とも連携し、ほたて種苗の安定確保を図るためのラ
ーバ調査を実施するとともに、購入漁協のニーズに対応するため、育
成篭への収容枚数の上限を定めることで、大型で統一された健苗貝の
確保に努め、販売数量の拡大を検討する。
・噴火湾では、ほたて貝のへい死は約5年毎に発生していたが、ここ数
年は毎年発生し、魚価も生産量も過去最低を記録し漁家経営が危機的
状況にある。その対策が急務とされており、そのため当該漁業協同組
合も加入している噴火湾ホタテ生産振興協議会(噴火湾全域の漁業協
同組合が加入している)が計画する漁場環境保全対策の実施とへい死
対策として漁場観測ブイを全域に設置し、噴火湾湾口からの影響や湾
内の海洋環境の変化を観測し、これにより得られた情報を漁業者に提
供し、そのデータを基に漁業者が漁場環境保全を図り、より高度な養
殖管理を行いへい死率を低減し、安定的な生産を図り漁家経営の安定
化を図る。
・なまこ桁網漁業者11経営体、採介漁業者37経営体及び漁協は、試
験研究機関の調査に基づき、産卵時期に禁漁期間を設けることで自然
産卵数の増大を図るとともに、操業時間の短縮及び栽培公社の協力を
得て5万粒のなまこの種苗放流・効果調査にも取り組むことで、資源
の増大に努める。また、部会を組織し、資源管理と併せ市場への出荷
方法について検討し、市場のニーズに合った出荷日、出荷量を定める
等、更なる単価の安定・向上を図る。
・採介漁業者37経営体及び漁協は、近年漁獲量が増加しているあわび
について、操業時間・漁獲サイズの制限による資源管理を行う。ま
た、栽培公社の協力を得て2万粒のあわびの種苗を放流し、一部にタ
グを取り付け追跡調査に取り組むことで、当海域におけるあわびの生
態系を調査し、将来に向けて資源の増大を図っていく。また、部会を
組織し、資源管理と併せ市場への出荷方法について検討し、市場のニ
ーズに合った出荷日、出荷量を定める等、更なる単価の安定・向上を
図る。
・ほっき桁網漁業者8経営体は、漁場地質調査を実施し、適地に稚貝の
放流を行うほか、研究機関等の協力により資源量を把握し、漁獲量上
限の設定や殻長制限などにより、適正な漁獲管理に努める。また漁場
耕耘やヒトデなどの有害生物駆除等を行い生産力が低下した漁場の再
生にも取り組む。さらに、再生した漁場への稚貝放流に取り組むほ
か、蓄養施設の導入による「活」保管を行うことで消費地市場の市況
を勘案した出荷調整や直売・オンラインショップを含めた販売方法を
検討する。
・全漁業者及び漁協、室蘭市は追直漁港の屋根付岸壁の早期整備を開発
局へ要望するとともに、高度な衛生機能を持つ荷受施設や滅菌海水設
備・海水冷却装置・活魚水槽等の整備を検討し、その活用による魚介
類の品質保持と鮮度向上、こんぶ等の種苗の自家生産を図るととも
に、出荷時期を調整することによる魚価の向上を図る。また、漁業
者・漁協職員・仲買業者を対象とした衛生管理研修会を実施し、衛生
管理意識の啓発・普及に努める。
・全漁業者と漁協は、イタンキ漁港の近隣に移転となった公設市場と協
議し、魚介類の販路拡大・市場ニーズに合わせた受注販売等に取り組
むべく、長期保管が可能な冷凍・冷蔵施設の整備を含めた販売戦略に
ついて検討する。また、刺網漁業者24経営体及び漁協は、漁協で新
設した製氷施設で作られる角立ちが少ないプレート氷や鮮度保持効果
が高い窒素氷の使用により、すけとうだら・かれい類の鮮度及び品質
向上を図る。さらに、漁協と漁業者はその効果を市場とも協議し、鮮
魚の取扱いが多いイタンキ漁港に貯氷施設の建設を検討する。
・全漁業者と漁協は、青年部及び女性部などと連携し、販売戦略に基づ
き、地元市民や児童生徒を対象に、室蘭地域の水産業のPRを踏まえ
た「ふるさと漁業体験学習」、「料理教室」を開催するほか、噴火湾
胆振海区漁業振興推進協議会と連携して、市内、小中学校の学校給食
へサケやホタテの提供を行うなど漁業への理解と魚食普及の推進を図
るとともに、市場と連携し、直売やオンラインショップ販売、ホーム
ページの活用により、室蘭産水産物の知名度向上と販路拡大に努め
る。
・全漁業者と漁協は、地元の一大イベントである「室蘭さかなの港町同
窓会」を継続開催し、魚介類のPR活動を行うほか、その他のイベン
トにも積極的に参加し、魚食普及・販売促進に取り組む。
■これらの取組により基準年に対し0.2%の漁業収入向上を目指す。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。