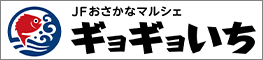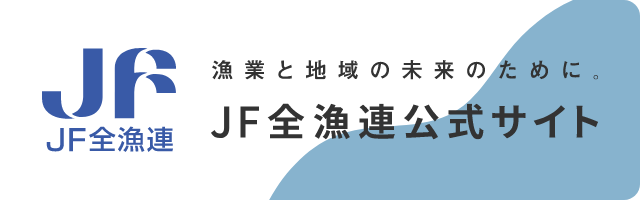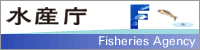浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
(1)資源増大・漁場環境保全対策
①貝類漁業者(102経営体)は、荒廃した漁場を全組合員に開放し、手掘りによる
耕耘を行い、漁場造成をするとともに、併せてヒトデ等の有害生物駆除を行
うことで稚貝の自然発生を促し、資源回復・漁場造成・生産力強化を図る。
また、畜養施設を活用し、消費地市場の市況などを勘案して出荷調整をする
ことにより魚価の安定と向上を図る。
②刺網・小定置・底建網・待網漁業者(93経営体)と根室湾中部漁協は、カレ
イ・チカの種苗放流に引き続き努める。また、ワラズカは本操業へと移行さ
れたが、資源量は未だ低水準であることから、引き続き、研究機関の協力の
もと、隣接組合と連携して市場出荷日(操業日)を統一して販売可能数量を確
保し、単価の安定・向上を図る。
③桁曳網漁業者(18経営体)と根室湾中部漁協は、ヒトデ等の有害生物の駆除を
行い、漁場耕耘に努める。継続してきたホタテ稚貝放流事業は引き続き適地
の選定に取り組む。さらに追跡調査も併せて行い、資源の活用と効率的な操
業サイクルのさらなる確立を目指す。また、漁業者と根室湾中部漁協は、ウ
ニ種苗生産施設を活用し、ウニ種苗の放流を継続し、資源の安定と増大を図
る。
④えびかご漁業者(29経営体)は、着業隻数・かご数・操業日数の制限を行って
おり、前浜海域で母エビを確保し、根室市と連携して稚エビの種苗生産及び
放流を引き続き実施し、資源の維持・増大を図る。また、操業前に資源量・
脱皮・抱卵状況の調査で適正な操業時期の把握と漁休日の設定などの取り組
みは継続して実施し、資源の安定と回復を図る。さらに、水揚後に漁業者自
らが行っているボイル加工については、保健所等の指導を遵守し、衛生管理
の徹底を図る。
⑤かにかご漁業者(6経営体)は、資源回復のため、関係する根室管内6漁協、1市
1町で構成する「根室海域ハナサキガニ資源対策協議会」と連携し、根室市
水産研究所が生産した稚ガニの放流事業や漁獲許容量の設定をしている。今
後も持続可能な漁業とするため、漁獲許容量の一部返納などを継続する。ま
た根室市が中心となって実施する「カニ祭り」を通じて一層の消費拡大や観
光客誘致のための情報発信にも取り組む。
(2)流通・付加価値向上対策
①さけ定置漁業者(15経営体)は、魚価の向上と維持を目的に水揚後の冷却水タ
ンク保管の他、漁船の魚倉に海水氷等を投入し、運搬するなど水揚から出荷
までの低温管理(5℃以下)を徹底することで、鮮度保持・衛生管理強化・魚卵
歩留まり向上を引き続き図る。
②さんま棒受網漁業者(2経営体)と根室湾中部漁協は、流通業者等からの鮮度
保持や衛生管理に対する要望に引き続き応えるため、根室漁協と協力し、漁
獲後のロス低下と付加価値向上の観点から、引き続き魚体温度管理を徹底で
きるタンク販売を行っていく。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。