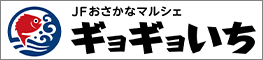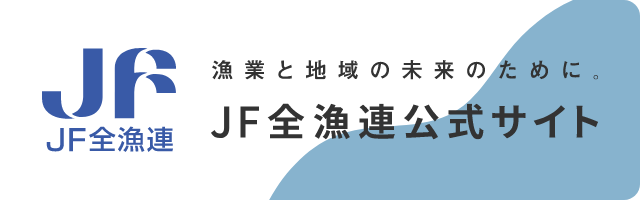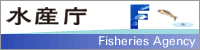浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
1)漁場の環境保全・資源の造成・生産の増大
①【漁場改善対策】
○取組内容
(大型魚礁などの設置による漁場造成)
・ひやま漁協及びせたな町は、種苗放流を行っているキツネメバル等、根
付資源を中心に、対象魚種の生態に配慮した放流から育成、漁獲までの
効果的な流れを構築するため、北海道へ保護育成礁等の整備促進を要請
するとともに、関係機関と連携し、種苗放流量を増大させることで、定
着性水産資源の維持増大を図る。
(豊かな藻場を造成する為の磯焼け対策への取り組み)
・町内藻場保全活動組織(4組織)が中心となり、魚類の種苗放流効果を
増大させるための産卵場所の確保や、前浜の主要資源であるキタムラサ
キウニの歩留向上のため、これらに繋がる藻場の保全や再生へ向け、ウ
ニの密度管理の徹底や、母藻の設置など、磯やけ対策の活動強化を図
る。
(漁場環境改善のための維持保全活動)
・全漁業者及びひやま漁協、せたな町は、地域住民や遊魚団体、小中学生
と協働して植樹活動や魚道、海岸の清掃活動などを行うとともに、地元
の子供達を対象に、漁業者が行う藻場の保全活動の理解増進を深める活
動を行う。
②【資源増大対策】
○取組内容
(秋サケの健苗生産と回帰率の向上へ向けた取組み)
・ひやま漁協及びさけ定置網漁業者(48名)は、日本海さけます増殖事業
協会との連携のもと、稚魚の生産について、親魚確保、採卵時期におけ
る前期群集中の体制から、中期群とのバランスを調整することで、飼育
密度の低減を図り、健全な稚魚を生産するとともに、来遊時期の海水温
を考慮し、中期群の割合を高める取り組みや、飼育施設における疫病対
策を引き続き実践することで、生存率及び回帰率の向上を図る。
(サクラマス資源回復のための遡上環境の整備)
・サクラマス資源は、回帰資源に含まれる天然魚の割合が高い知見がある
ことから、ひやま漁協及び関係漁業者(一本釣(83名)、小定置(1
名))は、せたな町と連携し、地域住民から要望がある漁場形成に繋が
っていた河川を中心として、防災上の検証が十分に行われた上で、ダム
のスリット化について関係機関へ要望を行うなど、天然魚による資源増
大を図る取り組みを展開する。
(マナマコ種苗の放流数拡大による資源の増大)
・ひやま漁協及びせたな町は、前浜の重要資源となっているマナマコの資
源増大のため、稚ナマコ生産・放流の増大を目指し、管内及び町内に設
置されている種苗生産施設(北海道栽培漁業振興公社、せたな町水産種
苗育成センター、ひやま漁協種苗生産施設)において、生産技術の向上
のための連携を強化しながら、給餌方法の効率化、飼育密度の検証や疫
病対策を徹底し、生残率の向上、生産数の増大を図る。また、久遠地区
なまこ漁業者(47名)による荷捌き所を活用した採苗と稚ナマコ放流な
ど、漁業者自ら行う取組みを併せて推進し放流数の拡大を図る。
また、全なまこ漁業者(165名)による操業日誌の作成を徹底し、適正
な資源管理や人工種苗の放流効果把握に努め、将来の事業展開へ向けた
基礎資料としていく。
(種苗放流による資源増大の取り組み)
○取組内容
・エゾアワビ
採介藻漁業者(116名)は、前浜の重要資源と位置づけているエゾアワ
ビについて、せたな町水産種苗育成センターと連携し、中間育成された
種苗を活用しながら、引き続き資源増大を図る。
・キタムラサキウニ
海外や国内外食産業の需要増大に伴い、高価格で推移しているため、う
に漁業者(138名)は、資源増大を図るため、未利用漁場からの移植に
よる資源管理を実施しながら、安定出荷に係る体制を引き続き強化す
る。
また、将来の資源不足に配慮し、青年部層が中心となり、未利用漁港施
設を活用した種苗生産について検討を行う。
・キツネメバル
ひやま漁協及びせたな町は、地域の回遊資源の漁獲変動が著しいことか
ら、根付資源であり、将来有望視されている高級魚の1つであるキツネ
メバルの資源増大を図るため、資源定着に繋がる大型魚礁の整備促進を
関係機関へ要請するとともに、一本釣り漁業者(83名)が中心となり、
これまで実施してきた種苗放流の継続や小型魚の保護等、資源管理を徹
底することで、資源の維持拡大に取り組む。
・ヒラメ
ひやま漁協は、資源量安定のため、北海道栽培漁業振興公社と連携した
種苗放流を引き続き行うとともに、関係漁業者による適正な資源管理や
適地放流の徹底を推進し、生残率の向上や資源の増大を図る。
・ニシン
回遊性資源であることから、広域で連携した取り組みにより効果が高ま
ることから、檜山管内の全町と八雲町熊石、ひやま漁協で構成する「檜
山管内水産振興対策協議会」が中心となり、北海道と連携し、檜山地域
のニシン資源復興へ向けて、種苗放流や孵化放流試験、生態調査など幅
広い取り組みを協働して行うことで資源増大に努める。また、回遊経路
や有効な漁場などの情報収集に努めながら、着業者を増やす取り組みを
並行して展開していく。
・新たな資源づくりへ向けた種苗放流の検討
上記のほか、近年の環境変化に対応した新たな資源の可能性や種苗生産
について、関係機関と連携して取り組む。
③【養殖事業対策】
○取組内容
近年、回遊性資源の来遊量の減少に伴い、これらを主力とする漁船漁業者
の水揚高は、減少の一途を辿っていることから、漁船漁業と養殖漁業によ
る複合的な経営や、漁業現場における多角化、協業化を推進する。
(ホタテガイ等2枚貝養殖の拡大)
・ホタテガイ養殖漁業者(13名)は、長期養殖の斃死リスクが依然として
高い状況であることから、第1期に引き続き、2年貝中心の養殖を展開
しながら、海外への共同出荷の取り組みを継続し、これに対応する生産
及び出荷体制の強化と、適地調査を行いながら、養殖施設の規模拡大に
ついて推進していく。また、種苗産地からの移入を従来の1年貝から当
年貝へ変更し、地域の海域に適合したものを選別して育成するなど、従
来の管理方法の見直しや新たな管理方法を試験的に導入していくことと
とし、斃死率の低減に繋がる手法を関係機関と模索する。
また、関係漁業者は、第1期で開始したエゾバカガイ養殖等、他の2枚
貝養殖に係る試験を継続し収益性など課題の検証を引き続き実施する。
(キタムラサキウニ養殖の推進)
・うに漁業者(138名)は、短期間で計画的かつ安定した水揚げが見込め
る養殖業の取組を進める必要があるため、第1期で取組みが始まった、
漁船が減少傾向にある漁港を有効活用した蓄養や短期養殖、篭養殖によ
る需要期対応(「早出し、遅出し出荷」)を引き続き推進し、増収を図る
こととする。
長期養殖においては、身入や色彩を考慮した安定的で低コストな餌料の
確保が増収へ向け必要であることから、関係機関と連携しながら検証を
行う。
2)水産物の単価向上、販路拡大対策
①【付加価値向上対策】
○取組内容
(鮮度保持の徹底、ブランド化の推進)
・鮮度保持、付加価値向上全般
衛生管理徹底のため、船上での漁獲物の取り扱いについて、殺菌海水を
用いた活魚水槽での活保管や活締めに加えて施氷による低温管理の徹底
など、対象魚種の選定を含めて検討を行うとともに、漁業者及び市場職
員の衛生管理の意識向上を図るための衛生管理講習会の開催などについ
て検討を進めるほか、加工品においては、6次産業化の推進を基本と
し、高品質な製品作りへ向け、先進的な冷凍技術の導入や、漁業者が共
同で利用する施設や機械導入を検討する。
・イカの鮮度保持
関東地方出荷向け(荷受午前6時まで)と札幌市中央卸売市場出荷向け
(荷受午前1時30分まで)の2系統で出荷が行われているが、6月〜8月上
旬にかけては札幌市場向け出荷の単価が高い傾向にあることから、同期
間における需要動向を確認しつつ、可能な範囲で札幌市場向け出荷の比
率を高め収入の増加を図る。
・タコの鮮度保持
一部の荷受施設では、タコの荷受において活魚水槽が設置されているも
のの冷却システムが無く、毎年6月以降、海水温の上昇により活出荷が
出来ず単価の低い生鮮出荷となっている。このことから、ひやま漁協は
荷受体制を整え、第1期に引き続き冷却システム活魚水槽設置施設へ水
揚げを集中化するとともに、漁業者は、出荷方法の統一ルール(船上で
の活魚出荷に向けた施氷による海水5℃前後の温度管理)を徹底し付加
価値向上対策に取り組む。
・エビの鮮度保持
えび篭漁業者(3名)及びひやま漁協は、買受け業者を通じて消費地側
からの要請を踏まえ、エビの色合いなどに配慮した鮮度保持、品質向上
に努めるべく、出荷方法の統一ルール(船上での搬送には海水殺菌及び
冷却装置を活用して、海水を5℃前後として温度管理を厳格に行う)を
定める。これをPRすることで、消費地側からの更なる信頼性の向上に
努めるとともに活魚出荷の比率を高め収入の増加を図る。
・ノリブランド
当地域の「ノリ」は厳冬期に採取し、寒い作業所での下作業、寒風での
りを乾燥させるため、地元では寒のり(かんのり)と呼ばれ、「無添
加」で磯の風味豊かな製品であるが、熟練した技術と作業が必要であ
り、付加価値を付けられる反面、数量不足の状況であるため、ひやま漁
協及び生産者(60名)は、新たな作り手の育成や、広域的な原料供給、
効率的な作業体制の構築による増産を推進する。また、せたな町と連携
し、この「漁師の技術」「手造り」の強みを活かしたブランド力のある
商品を都市圏でのPR活動並びに販売促進によって知名度の向上、販路
の拡大を図る。
・ブランドエゾアワビ「蝦夷鮑華」の販売促進
漁業者が厳選した150g以上の大型のエゾアワビについて、「蝦夷鮑華」
と命名し、第1期プランにおいて、商標登録、ブランド化を行い、販売
が開始されたことから、ひやま漁協が関係機関と連携し、販売拡大へ向
け、ふるさと納税返礼品や、都市部をターゲットとした催事等での販売
PR、資源造成のための取り組みを等を引き続き展開していく。
②【6次産業化の推進/販路拡大対策】
○取組内容
(6次産業化の推進/都市でのPR活動並びに販売促進による知名度の向
上)
・せたな町及びひやま漁協は、6次産業化や漁業者自らの加工等を推進す
るとともに、関係機関が連携し、既存の海産物や加工製品の磨き上げ、
新たな商品開発、販売促進を展開することとし、協働して、札幌圏での
販売イベントの実施や、町の観光部署が実施する道内外で行われるPRイ
ベントへの参加を通じて各製品の知名度向上や販路拡大を図る。
③【都市漁村交流、食育対策】
○取組内容
(都市漁村交流)
・せたな町及びひやま漁協は、せたな観光協会、関係団体が実施している
修学旅行の誘致事業と連携し、漁業又は水産加工等に係る体験メニュー
を盛り込みながら、都市部との交流を図り、町の水産物に関する理解を
深めてもらうなど、PRに繋げる。
(食育対策)
・せたな町及びひやま漁協は、地元の小中学生を対象に、うに漁業やさけ
定置漁業、各種種苗放流事業の参加と合わせ、これらを活用した郷土料
理の調理、試食などを企画し、地元水産物の素晴らしさや食に関する理
解を深める機会を設置する。
学校給食における食材利用は、コストやメニューなど、関係機関との調
整が必要なことから、第1段階としてスポット的な実施へ向けて検討を
行う。
3)担い手の確保・育成
①【担い手の確保・育成】
○取組内容
(担い手確保・育成のための体制整備)
・町の人口減少や高齢化が進む中、漁業者も同様の状況であり、水揚減少
の大きな要因となっていることから、せたな町とひやま漁協が連携し、
北海道漁業就業支援協議会事業や町の就業奨励制度を活用しながら、新
たな担い手の確保に努める。
また、漁業権行使規則や漁業部会で定めるルール等、新規組合員の確保
へ向けた見直しや、操業の指導体制など、地域全体で担い手を受け入れ
るシステムづくりへ向け、検討を重ねる。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。