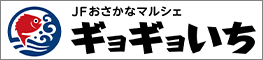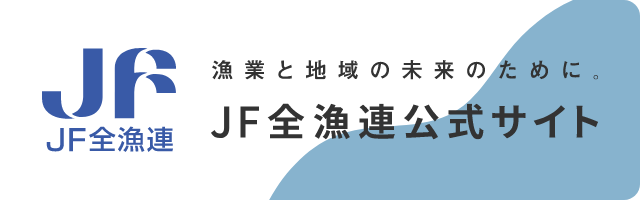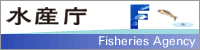浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
(1)水産資源物の適切な管理と維持増大
①栽培漁業と水産資源の適切な管理
・漁業者は、漁獲物の禁漁期間や体長制限の遵守など、資源管理について
の取組を進める。
・漁業者は、年度内に夷隅東部漁協資源管理計画から資源管理協定への移
行を県の指導助言を受けながら完了するとともに、協定に基づく資源管
理に取り組む。
・漁協と漁業者は、「第 8 次千葉県栽培漁業基本計画」に基づき、ヒラメ、
マダイ等の種苗放流を行う。また県が実施する種苗放流試験や市場調査
等に協力する。
②環境や生態系保全活動の積極的な推進
・漁協と漁業者は、県の協力のもと、藻場モニタリング調査や植食性魚類
の全数持ち帰りなど、藻場の現状把握と保全活動に取り組むほか、「外房
磯焼け対策チーム(夷隅)」の会議や研修会に参加し、地域全体で藻場の
保全活動を進める。
(2)漁協DXの推進
①地域の経済活性化
・市や漁協、県が主体となって、港活性化協議会を設立する。協議会は、(株)
SOTOBO ISUMI等と連携して、農山漁村振興交付金(地域活
性化対策)事業への申請と交付を受け、協議会構成員の意思確認及び方
向性の決定を行い、地域活動計画を策定する。
・港活性化協議会は、地域活動計画の目標達成に向け、協議会構成員と協
議会協力機関でワークショップを開催し、方向性の確認や情報共有を行
う。
・協議会構成員だけでは情報量や経験が足らず、目標を達成することは困
難なことから、水産物の取扱い方や市場調査方法、漁業者の働き方の変
革、生産者の意識を高めるための情報発信などについては、漁協と協議
会協力機関が中心となって、専門的スキルを有する人材の協力を得なが
ら進め、地域の稼げる力に磨きをかける。
②スマート水産業の推進
・漁協と漁業者は、(株)SOTOBO ISUMIや北海道大学、民間企
業、県等と連携し、鮮度測定(K値)機器の開発や、市販の脂質測定機
器を導入し、「鮮度の見える化」の実証試験に取り組みながら、鮮度管理
の重要性を認識し、高鮮度な大原産水産物の出荷を目指す。
・漁業者は、県が所有する簡易CTDを用いた漁場の水温観測を行う。県
は、漁業者の操業効率化を進めるため、観測データを用いた海況予測シ
ステムの運用を開始する。
③漁協DXの推進
・漁協は、市や(株)SOTOBO ISUMI等と連携し、デジタル計
量や水温塩分管理、電子入札など漁協DXに必要なシステムの運用を開
始し、入札業務の簡素化、効率化に取り組む。また入札時間の前倒しに
ついて、漁協内で検討を始める。
(3)大原産水産物の販路拡大と魚価の向上
①鮮度向上の取組推進
・漁協は、市や県と連携して老朽化した製氷貯氷施設の更新に向けた実施
設計を行う。
・漁業者と漁協は、外部専門家による漁獲から入札までの活魚の取扱いや
船上活〆等の鮮度保持、市場での鮮度管理等の評価や研修会、指導を通
じ、より高鮮度の水産物を提供するための技術習得を図る。また鮮度管
理に必要なクーラーボックスやダンベなどの保冷容器等の資材を導入す
る。
②水産バリューチェーンの構築
・改善部会は、大原産水産物の知名度向上や販売促進に向け、部会構成員
への情報提供や共有を図るほか、バリューチェーンの構築を進める上で
の課題の抽出とその解決に向けた協議を開始する。また、協議内容を踏
まえ、大原産水産物の知名度向上や販売促進に向けたPRイベントに参
加する。
・漁協は、「いさばや」に生産目標に応じた規模の急速凍結機を導入し、高
鮮度の大原産水産物を用いた急速凍結加工品の開発や製造に取り組み、
安定した供給を目指す。また市場において水産物の買い支えを行い、魚
価の維持、向上を図る。
・市と漁協は、地域活性化に向け、地元飲食店や観光業者と連携し、水揚
げが増加している大原産トラフグやショウサイフグなどのふぐ類を用い
た「ふぐの町づくり計画」の策定に向けた検討や協議を行う。
・漁協や漁業者、市は、地元飲食店や都市部のデパート等と連携した大原
産水産物のPRフェアに参加し、知名度の向上を目指すほか、外部専門
家の指導助言を踏まえたマーケット調査に取り組み、消費者ニーズの把
握を行う。
③大原産水産物のブランド化
・漁協は、県の指導助言を受けながら、「船上活〆サワラ」の千葉ブランド
水産物の新規認定申請を行い、認定を目指す。また、既に認定を受けて
いる「いすみ産マダイ」及び「いすみ産大さざえ」については、県の指
導助言を受けながら、再認定申請を行い、認定を継続させる。
・漁協や市は、漁業者や市場職員、地元仲買業者を対象とした外部専門家
によるトラフグの取扱い方研修会を開催し、活魚の適切な取扱いや神経
〆による高品質な「大原産トラフグ」を出荷するための技術習得を進め
る。漁協は、県の指導助言を受けながら、市や漁業者、地元仲買業者と
千葉ブランド水産物認定に必要な「ブランド産物名」や「旬」、「販売規
格」、「統一した取扱い方法」などについて協議を行い決定する。また、
次年度以降に取り組む主要な出荷先である豊洲市場や都内飲食店等での
PR活動内容について、外部専門家を交えて検討を行う。
・漁協や漁業者、地元仲買業者は、県等が主催する千葉ブランド水産物の
PRイベントや販売活動などに参加し、知名度向上と販路や消費の拡大
を目指す。
・漁協や地元水産加工業者は、自らが製造する水産加工品について、県や
市から鮮度管理や衛生管理、販売促進等の指導や助言を受け、千葉ブラ
ンド水産物の認定を目指す。
(4)観光等と連携した地域水産物の知名度向上や消費拡大の取組推進
①地元観光イベントでのPR活動
・漁協と漁業者は、市やいすみ市観光協会等と連携して取り組んでいる地
域観光イベントの「大原漁港 港の朝市」において、大原産水産物のP
Rや販売を行う。また千葉ブランド水産物の「外房イセエビ」を用いた
「いすみイセエビ祭り」(8~10 月の毎週日曜日)や「太東・大原産真蛸」
を用いた「たこしゃぶ祭り」(1 月中旬~3 月中旬)を季節イベントとし
て朝市と同時に開催し、旬の大原産水産物の良さを味わってもらう。
・漁協女性部は、地元伝統食の「たこ飯」やサメ肉を用いた「じあじあ」
の製造と販売を継続して取り組み、来場する幅広い世代にPRするほか、
県外の未低利用魚活用グループが取り組むサメ肉を用いたシュウマイの
開発に協力する。
②地元水産物等の魅力発信
・漁協は、SNSを活用して地元水産物の魅力を積極的に発信する。
(5)安全・安心な水産物の提供
・漁協は、衛生管理マニュアルを策定し、市場における衛生管理に努める
とともに、漁業者と関係者は、マニュアルに基づいた水産物の取扱ルー
ルを遵守し、安全・安心な水産物の提供を行う。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。