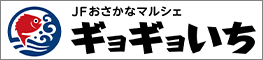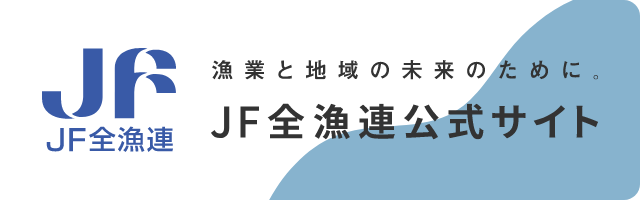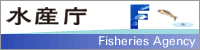浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
以下の事業に取り組み、漁業収入を向上させる。
(1)加工事業の体制強化、魚価の安定化、水産物の消費拡大
・漁協は、前期の浜の活力再生プランでの取り組みや得られた成果等を踏まえ、課題とな
っている加工事業の経営計画を策定する。
・漁協は、加工事業の拡大のために、急速冷凍を用いた水産加工による生産体制の強化を
検討する。
・小型底曳網漁業者、定置網漁業者、漁協は、大量漁獲で値崩れするメギス・ナンバンエ
ビについて、大量漁獲時等に一部を加工原料用に回し市場出荷された魚価の下落を防止
し、かつ、需要が見込めるドレス等の加工品の生産に取り組む。また、その他の魚種は、
断熱コンテナで取引事業者等へ出荷することを検討し、漁業者の経費削減に努める。
・漁協は、学校、介護保険施設等について、それら施設の栄養士や調理員との懇談会を行
い、加工品の利用促進を継続的に働きかける。
・小型底曳漁業者は、船上から動画や画像等で発信し、単価の向上を図る。
・神経締め等の付加価値を高めた鮮魚の取り扱いに取り組む。
・漁協は、水産物の消費拡大を図るため、市内で行われる料理教室などにアジ等の鮮魚や
ニギス等の加工品を提供するとともに、糸魚川市地産地消推進店に認定された飲食店を中
心に、市内店舗への安定的な供給や販路拡大を推進する。
・漁協は、県、市と連携をして、魚食普及を行い、水産加工品および鮮魚の販路拡大に努
める。
・漁協及び漁業者は、取り引きする店舗等での販促イベントを行い、県内外での販路拡大
を推進する。
(2)衛生・品質管理の徹底
・漁協は、水産物産地における衛生・品質管理を強化するため、荷捌き所、市場での汚染
防止対策に取り組む。そのために定期的に衛生管理講習会を開催し、荷捌き所、市場等の
漁協関連施設の清浄化、水産物の高品質化、市場関係者の衛生管理に対する理解を深め
る。
・これまでの検討を踏まえ「衛生・品質管理マニュアル」策定の検討を進める。
・小型底曳網漁業者、刺網漁業者、釣・延縄漁業者、カニ籠漁業者、漁協は、水揚げ後の
鮮度低下を防止するため、漁獲物の先出しを行い、他市場と違いを図り、魚価の向上に努
める。
(3)収益性の高い経営体の確保
・収益性の高い新たな経営体の確保を図るため、漁船及び漁船設備等の導入についての取
組みを継続する。
(4)資源管理と漁場環境保全
・漁業者は、資源の維持・向上を図るためヒラメやアワビ等の種苗放流を実施するととも
に、関係漁協、関係市、県水産海洋研究所、県水産振興協会等と協力して、これまでの効
果の検証と放流内容の検討結果を踏まえ、種苗放流を実施する。
・また、大型クラゲ等の有害生物の除去により漁場環境を保全し、作業効率の向上、漁獲
物の品質低下の防止、漁具の破損防止を図る。
(5)施設の維持管理
・漁業者及び漁協は、漁港及び漁業関連施設の定期的な点検や異常気象時の見回りによ
り、漁港機能の維持や安全・安心な漁業活動が行えるよう適切な維持管理に取り組む。
・漁港および漁業関連施設の機能集約の検討を進める。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。