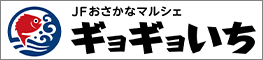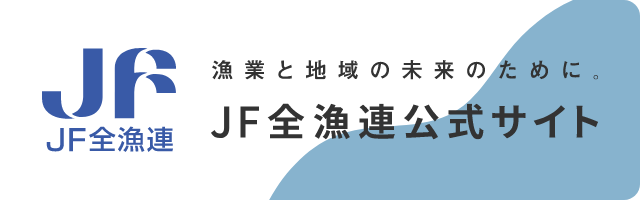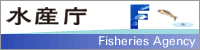浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
①資源管理と外来魚駆除による漁獲量の確保
1)資源管理型漁業(資源の状況に対応した漁獲の実施)の推進
漁業者は、漁業調整規則等で規定されている採捕禁止期間や全長制
限等の公的資源管理措置を遵守し、操業をおこなっているところであ
る。
今後とも、公的資源管理措置を遵守し操業するとともに、漁業者間で
の操業隻数や操業日数の調整による水産資源の状況に対応した漁獲の
実施など、資源管理型漁業の一層の推進による資源維持と安定供給に
努めながら漁獲量の増加を図る。
また、滋賀県で開発された「湖(うみ)レコ」を積極的に活用し、資
源管理型漁業の一層の推進による資源維持と安定供給に努めながら漁
獲量の増加を図る。
2)外来魚駆除による資源の保全
琵琶湖漁業に深刻な被害を与えているオオクチバス、ブルーギルな
どの外来魚は、通常の漁業によって捕獲される駆除のほか、駆除目的の
沖びき網による積極的な駆除等により、生息量は減少傾向にある。
在来魚の回復のためには、更なる駆除が必要となっており、一層の外
来魚駆除に努めることにより、水産資源を回復し、漁獲量の増加を図
る。
②6次産業化の推進
1)湖魚の冷蔵保管施設、処理加工施設の整備・充実
沖島漁協では、高品質なビワマス・ホンモロコの冷凍品を漁期以外に
県外市場に安定供給することを目的とする「ビワマス・ホンモロコ安定
出荷体制整備パイロット事業(事業主体:滋賀県漁業協同組合連合会)」
を実施し、高品質なビワマス・ホンモロコの供給体制の確立を目指して
取り組んできた。
パイロット事業の成果を踏まえた高品質冷凍設備等の設置による
「沖島の味」の高付加価値化のための品質保持に加え、一次加工や「沖
島グルメ」の開発等に資する湖魚の処理加工施設の整備・充実に向けた
検討を行う。
2)沖島の食文化を味わえるレストラン・直売所等の整備
湖島婦貴の会(沖島漁業協同組合婦人部)では、伝統的な湖国の食文
化を活かし、沖島で水揚げした新鮮な湖魚を炊き上げた若煮、お弁当、
沖島物産品の加工販売を行っており、「沖島の味」とくつろぎを来訪者
に提供している。
しかしながら、現在「沖島の味」の加工販売は、漁協会館のスペース
を借用した限られた施設で実施しており、増加する来訪者のニーズに
十分な対応ができていない。
そのため、調理加工施設、レストラン、直売所等の整備と供給・サー
ビス体制の充実が必要となっていることから、沖島の食文化を味わえ
るレストラン・直売所の整備に向けた検討を行う。
※上記②-1)及び②-2)は、漁業収入を向上させるための核となる
施設として、老朽化した漁業会館のリニューアルにより、冷蔵保管施
設、加工施設、販売・交流促進施設等をもつ沖島漁業会館へと再整備す
るものである。このため1年目は、施設整備計画や施設運営体制の構
築、「浜の活力再生交付金」の申請に向けた準備、検討を行う。
3)ふるさと納税返礼品の活用
「沖島の味」をふるさと納税返礼品として商品化を検討する。
③認知度の向上と販路の拡大
1)「沖島の味」の認知度向上と普及促進
インターネット等を活用し、アユの山椒入り若煮、エビ豆若煮、ハス
田楽、鮒ずし、ハスのめずしなどの「沖島の味」を中心に消費者への直
接販売や「鮒ずし手作り講習会等の体験交流事業」などを促進させるた
め、漁協ホームページを拡充する等のPR活動を強化する。
加えて、地元商工会議所や JA 等が開催する地域のイベントへ出店
や滋賀県のアンテナショップ「ここ滋賀」でのフェアの参加等により、
「沖島の味」の認知度向上と普及促進を図る。
2)湖魚加工食品の販路開拓・PR
滋賀県が推進する「琵琶湖八珍」ブランド化事業と連携したイベント
等への参画や、「琵琶湖八珍マイスター店」等への沖島産湖魚や加工品
の販路開拓・拡大化を推進する。
3)未利用魚の活用・商品化の推進
未利用魚を原料とする商品の加工・販売を検討し、未利用魚の有効活
用を図る。
④漁業関連従事者の育成・確保
1)新規就漁者の受入れ
沖島漁協は、滋賀県漁業協同組合連合会に設置された「しがの漁業技
術研修センター」が受け入れる琵琶湖漁業に就業を検討する研修希望
者に対して、漁業体験研修、本格的な技術を学べる実地研修を行い、新
規就業者の確保に努める。
さらに、沖島独自での漁業体験事業の実施に向けた検討を行う。
⑤沖島独自の自然景観や暮らしの文化を生かした交流体験型観光の推進
1)「島の宝」を活用した交流体験プログラムの造成
春には“沖島桜まつり”の開催や“地引き網体験”等のイベントを、
初夏には滋賀県を代表する名産品である“鮒ずし”の漬け込み体験を琵
琶湖汽船とのタイアップ企画により開催し、好評を得ている。
さらに、沖島町離島振興推進協議会では、島に伝わる伝統や食文化、
四季折々の自然の風景など、島のよさを広く知ってもらい、島に来ても
らうことを目的とした、沖島ファンクラブ「もんて」の組織化と情報発
信、『沖島遊覧船もんてクルーズ』の運航、「聞き語り沖島の暮らし伝え
人」の発刊、フォトコンテストなどの交流イベントの開催なども実施し
ており、現行の交流体験型イベントや事業を強化するとともに、漁村留
学体験「おいでよ湖の学校」などの「島の宝」を活用した新たな交流体
験プログラムの造成による、誘客促進を図る。
また、これらの行事などの手伝いを行う学生ボランティアの受入れ
を進める。
2)渚泊の受入れ
地域おこし協力隊と協力し、空き家を活用し島民と宿泊客が交流で
きる民泊「湖心」を運営するとともに、観光客が沖島の生活を体験でき
る「渚泊」について検討する。
⑥安全・安心な生活環境の創出
1)空き家の活用等による移住、定住の推進
島内には長年活用していない空き家が存在しており、それを U ター
ンした島民が改修して利用、テレワーク等新しい働き方に対応できる
ように空き家の整備を行う。
また、日用品の買い物支援や ICT を活用した独居人の見守り事業等
による定住を推進する。
2)防災・救急・救命体制の充実・強化
人家が密集する西南部の約 0.1k㎡の狭小な平地は、間近に琵琶湖と
傾斜の強い山肌が迫っており、災害時を想定した対策が必要となって
いる。島内の防災機能の強化充実に努めるとともに、避難所(地)、避
難道路、消防施設等の整備について検討する。
また、エネルギー供給を遮断されるような災害時等の事態に備え、島
が孤立しないための新たなエネルギー対策(環境負荷の少ない、地産地
消の再生可能エネルギー)の研究および太陽光発電・風力発電等の設備
導入について検討する。
3)島を訪れる人にも活用される広場、公園、休憩スポット等の整備
島を訪れる人にも活用されるよう、里山整備を行うとともに、既存公
園の再整備や新たな休憩スポット等の整備を検討する。
4)美しい島の維持と環境保全
観光客が何度も訪れたくなるよう美しい島を目指し、環境美化運動
を推進していく。
また、レストラン等の整備により、食料残渣が懸念されることから、
生ごみなど島内でリサイクルできる仕組みづくり(生ごみのたい肥化
施設の整備等)を検討する。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。