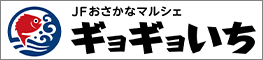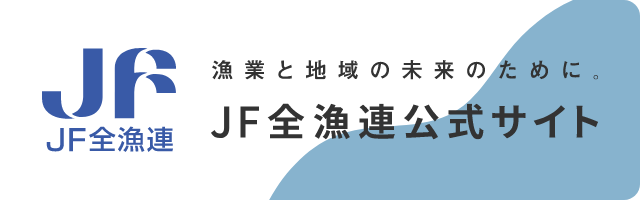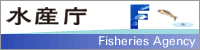浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
ア 魚価の向上
・漁船漁業者 92 名と漁協女性部 73 名は、漁協直営の「魚魚市(とといち)」や、
「室乃津祭」、「室津かきまつり」等のイベント開催において、地元水産物(シ
タビラメ、ガザミ、カキ等)の直売や海鮮汁の試食、魚のつかみどり大会等の
実施により、地元や都市住民に対して情報発信を行い、「魚の町室津」をPR
することによる地域水産物の知名度向上を図り、消費拡大と単価の向上を目指
す。
・漁協女性部 73 名は、各漁業者と協力して、シタビラメ、グチ、アジのみりん
干し等を中心とした水産物の加工品製造を行い、付加価値の向上を図る。
また、加工するのに適した原材料(シタビラメ、グチ、アジ)が少ない場合で
も対応できる作業方法や、原材料がすぐに確保できないこともある為、原材
料の一時保管等を目的とした冷蔵施設などの購入も含め効率化、作業コスト
等の見直しを行い、さらなる付加価値向上を目指す。
・漁協女性部 73 名は弁当、総菜、その他加工品を製造する際に利用している包
丁やまな板等の調理器具を衛生面を考慮した調理器具に入れ替える。また調理
場なども衛生管理を徹底し弁当、総菜、その他加工品のさらなる単価の向上を
図る。
・値がつかない鮮魚を用いた商品(エイ・アジ・小型の舌平目、ボラ、グレ等を
ミンチにし、ハンバーグ、餃子、ツミレ等に加工したもの)について、新たな
商品開発に取り組むとともに、直売所「魚魚市」の弁当・惣菜等のコーナーで
販売を試み、販売先の確保及びそれに伴う魚価の向上を目指す。また、安価な
魚以外でも付加価値を向上できるような加工品ができないか試作・評価を行い
ながら浜値向上を目指す。
・漁協は、漁獲物について従来から使用している木製のトロ箱を随時プラスチッ
ク製のトロ箱に変更し衛生面の向上等を図るとともに、各漁業者は、活魚出荷
割合の増加等により単価の向上を目指す。(平成 26~30 年までに約 7 割変更済
み、33 年迄に全て変更予定。)
・漁船漁業者 92 名及び漁協は、漁村近郊の鮮魚販売施設「道の駅みつ」や「新
舞子ガーデンホテル」と連携し、鮮魚等の販売を推進し取扱魚種を増加させる
とともに、他の観光施設にも地元産の魚介類を販売できるように営業活動を行
い販売ルートの拡大を図る。
イ 資源の増大と漁場の回復
・漁船漁業者 92 名は漁協と協力して、ヒラメ、マコガレイ、ガザミ、クルマエ
ビ等の稚魚放流を実施する。また放流方法についても放流場所・放流方法など
確実的な放流方法を確立し実施する。
・各漁業者及び漁協は、県と共同で、マコガレイ、メバル、カサゴ、スズキ等を
対象とする西播磨増殖場造成事業を推進することで、これらの魚種の資源量増
加と漁獲量の向上を図る。
・各漁業者は、従来から実施している海底耕耘に加えカキ養殖の漁期の始めと終
わりの計 2 回、海底清掃を実施し、漁場環境保全に係る活動を推進する。
ウ カキ養殖の振興
・カキ養殖業者は、漁場環境のモニタリング調査を実施するとともに、養殖漁場
や養殖密度の検証を行い、より成長が良く効率的なカキの生産方法を確立す
る。
・カキ養殖業者は、兵庫県認証食品制度の認証を受けることができる高品質(一
粒 15g 以上・細菌数基準の合格など)のカキを生産するとともに、認証マーク
の貼付等によるPRを推進し、室津かきのブランド化を図る。
・カキ養殖業者は漁協と協力し県の指導を受けながら、他県に依存している養殖
用種苗を地元でも供給できるよう、引き続き採苗試験を実施し、全国的な種苗
不足時のリスク軽減及び種苗の安定供給を図る。
・カキ養殖業者は、荒天時に吊り線のカキが脱落して海底に落ちる「落ちガキ」
による被害を軽減するため、「落ちがきキャッチャー(※)」の導入を継続推進
する。
(※)同地区の漁業者が考案した養殖筏の吊り線下に設置する円形ネット。こ
れにより「落ちガキ」の回収が可能。
・カキ養殖業者はカキの殻が「キレイで、同じサイズ、同じデザイン」で提供で
きるよう「シングルシード(※)」を用いた養殖も取り入れ殻付きカキの単価の
向上を目指す。
(※)従来のホタテ貝の殻ではなく、牡蠣の殻を砕いて細かい粒にしたものを使
用し,水槽の中でカキの卵を受精させ、幼生になったころ、カキ殻の粒に付着
させ、水槽の中で、幼生をある程度の大きさの稚貝にして、網かごに移し替え、
海に沈める方法。また、シングルシードはゆったりしたかごの中で転がりなが
ら育つため身が丸く厚くなると言われている。
・カキ養殖業者は、カキとアサリの複合養殖の取り組みを進めることにより、カ
キ不漁による減収リスクを分散させ、副収入による経営の安定化と、アサリの
生産拡大を図る。
・アサリ養殖業者はアサリのふ化から稚貝になるまでの生産率を上げる方法を確
立し、種苗の安定供給を図るとともに、コストの削減にも取り組む。
エ 漁船漁業の効率化
・船曳網漁業者及び漁協は、新たに運搬船の大型化やクレーンの設置等による効
率的な漁業形態を検証し、漁船漁業の収益性改善を図る。
オ 魚ばなれの抑止
・漁協女性部 73 名は、料理教室等を通じて、地域の小中学生や食育活動を実施
している団体に引き続き魚食普及活動を実施し、地元水産物のPRを行う。
カ 漁業後継者の育成
・漁協は、健全な漁業経営と資源管理を行うことができる漁業後継者を育てるた
め、様々な分野の研修に参加できる体制を構築する。
・漁協は、新たに漁家の後継者候補に対する研修を実施し、新規就業者の確保に
努める。
キ 中核的漁業者の収益向上に必要となる漁船の導入
・船曳網漁業を営んでいる地元の中核的漁業者と漁協とが協力し、船齢が古く作
業スペースが狭く、故障等も多い船曳網漁船(運搬船・網船)を、浜の担い手
漁船リース事業等を利用し、漁業コストの削減、作業効率の向上を目的とした
漁船を導入し浜値の向上を目指す。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。