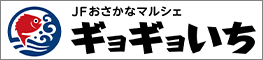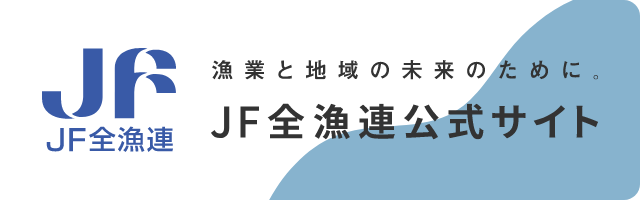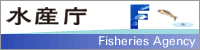浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
ア)直接販売の拡大
○ 島内の漁業者は、家島漁協と連携して、姫路市本土側の妻鹿漁
港において、「とれとれ直売」を推進する。
「とれとれ直売」では、地産地消を旗印に、アジ、メバル、カ
サゴ、イカ、サザエ(磯端漁業)、エビ、カニ、カレイ類、アナ
ゴ、ハモ(小型底曳網漁業)、イカナゴ、シラス(機船船曳網漁
業)等の鮮魚、活魚、味付海苔、焼き海苔の販売を姫路市及び近
郊の消費者を対象に販売するとともに、水産物の調理、食べ方等
を紹介することによる魚食普及や地元水産物のPR活動を実施
する。なお、これら取組みについてのPRは、新聞広告等も利用
する。
○ 漁業者(86 名)は活魚出荷等の直接販売に適した形態で消費
者に対する出荷数量を増加させ、魚価向上と販路拡大による漁業
収入の向上を図る。
鮮魚であれば、消費者は「スーパーなど量販店と同じもの」と
いう認識(錯覚)をもたれることから、可能な限り活魚で販売し、
その場で締めるなど一次処理を行う。活魚を前面に押し出すこと
で、より鮮度の良さをアピールでき、価格も高めに設定できるよ
うになる。
また、小売価格は、流通コストや仲買がマージンを取るため産
地価格の約3倍が相場であり、直売によって消費者には安く供給
することができ、双方にメリットが生じる。
この活魚販売を拡大するため、可動式2トン活魚水槽を4基増
設する。
磯端漁業(定置網漁業やカゴ漁業)では、ほとんどの魚介類は
漁獲時に元気に生存しており、小型底びき網漁業においても海中
から網揚げた時点でマダイやキジハタの成魚、アナゴやハモは元
気に生存している。ただし、小さい魚介類や、いわゆる青魚は、
水揚げ時点で死亡していることが多い。
これまでは、水揚げ時に生存していても、直売所でのキャパシ
ティがなかったため、販売時には鮮魚での販売となっていた魚介
類が、活魚水槽の増加により活魚での取扱量が増加する。
活魚水槽の増加に合わせ、漁業者は、死後始まる鮮度低下を防
ぐことができ、魚介類の取扱いが楽になる。(死ねば、保冷をし
なければならない。)
なお、夏季は船上におけるの温度上昇を防ぐため、海水氷を投
入することとしている。
この結果、直販では、客の前で、活かした状態で販売すること
ができ、地元産であることが証明されることとなり、かつ、締め
る(後頭部に包丁を入れて脊髄を切ること。)ことで、購入者も
最上コンディションでの魚介類を味わうことができるようにな
る。
イ)ノリ養殖業の収入向上
○ ノリ養殖業者(全9協業体)のうち8協業体が補助事業等で整
備した大型乾燥機を有効活用することにより、単位時間あたりの
生産枚数の増加と品質向上(異物混入等によるロス率の低減)を
6
行い、かつ、漁業者のノリ網の作付け柵数の増加によって、生産
量・生産金額の増加による漁業収入の向上を図る。
○ ノリ養殖業者は、漁協及び家島漁業集落と連携のうえ、健全な
種網(赤腐れ病や壷状菌に感染していないことが確認された病気
を持っていないのない種網、育苗管理という。)の確保と漁場で
の十分な管理(適切な干出作業、ノリ網洗浄、珪藻の付着を防ぐ
ための酸処理)を行う。
○ 出荷にあたっては、最新鋭のノリ選別機(金属探知機と重量選
別機が一連となった機器)を導入することで、より的確な等級づ
けが可能となる。この結果、浜の出荷体制が強化され、ノリ入札
業者(㈱☆☆海苔、△△屋㈱、㈱○○園などの買付商社のこと)
からの「浜としての信頼性(家島のノリはロット管理ができてい
て、同一ロットでの品質が安定している)」を高められ、浜全体
での価格の向上が図られる。
○ 兵庫県漁連では、新品種が順次開発されていることから、これ
ら新品種の導入を行い良質ノリの生産を行う。(なお、新品種の
性状については、種苗登録法で保護されるべき情報であるため、
ここには記載しない。)
○ さらに、各生産者は各々、常に、兵庫県水産技術センターが発
信する播磨灘海域における栄養塩の濃度やプランクトンの密度
情報、「溶存態窒素が何マイクロアトムス/リットルか」など、
常に漁場環境情報や気象、海象現況、予報を注視しつつ、自己の
の漁場におけるノリの生長状況(伸び足、色調)を見ながら、ノ
リの刈取り時期を決め、より良質なノリ(色が黒く光沢のあるノ
リ葉体のこと)が刈り取れるようにする(もし、栄養塩が低いよ
うであれば、刈取りを見送り、栄養塩の回復を待つこともあるた
め)。
○ 栄養塩低下によるノリ葉体の色落ち緩和策として、小型底曳網
漁業者、機船船曳網漁業者の協力のもと、海底耕耘による海底の
栄養塩溶出のための作業や自ら栄養塩添加を実施することによ
り、ノリの品質向上による漁業収入の向上を図る。
ウ)荒天時への的確な対応による効率的な操業の確保
○ 漁業者(86 名)は、漁協とともに、必要に応じて開催される事
業や工事の説明会議に出席し、県や市が策定する漁港整備計画案
について、県や市の職員からの説明を聞き、それに対して意見を
述べることにより、計画の策定に参画する。漁業者の意見が反映
された漁港整備計画に基づき整備されてきた漁港(妻鹿漁港、室
津漁港、岩見漁港、坊勢漁港など)に、荒天時には地元漁船(207
隻)をこれらの家島漁港以外の他港に避難回避させることで、休
漁時間短縮に伴う漁獲量の増大を図る。
家島は、播磨灘の北西部に位置する離島であるため、全方位から
風や波の影響を受け、特に、冬季北寄りの強い季節風が生じる悪天
候下では、出港すらできなくなる。そこで、荒天が予想される場合
は、他港、すなわち本土側の港にあらかじめ避難しておくことで、
北寄りの風であれば操業が可能となる。
エ)新規就業者の確保及びスキルアップ
7
○ 漁協は、漁業者の小型船舶操縦士免許、無線従事者免許取得等
の講習会参加を支援し、漁業者は、自ら漁業後継者の育成や労働
力の確保及び新規就業者の漁業法や漁業調整規則の内容、順法精
神、最新漁法等の習得によるスキルアップを通じた生産性の向上
に努め、これらを通じて、漁業収入の向上を図る。
オ)漁業情報の発信、都市住民との交流
○ 漁協は、自己が所有する漁船を活用し、観光と漁業を組み合わ
せた「漁業の体感・体験プログラム」の開発に取組む。
このプログラムでは、参加者(一般県民など)が当該漁船に乗
船し、海上で定置網や小型底びき網漁業また、冬季はカキ養殖場
に接舷し、それらを営む漁業者と直接ふれあい、互いに話ができ
る場を設けるとともに、家島の魚介類を食し、また購入できるよ
うな内容とすることで、漁業収入の向上を図る。
今年度は、モニターツアーを複数回実施し、参加者アンケート
から翌年度のプログラムにフィードバックさせる。
カ)水産加工品の開発
○ のり養殖業者は、これまで乾のりの出荷が中心であったが、保
存できるなど付加価値のある商品開発を漁協とともに取組むこ
とで、次年度以降の漁業収入向上を図る。
加工試験(のりの佃煮)は、漁協の調理加工室で行い、冷凍冷
蔵試験は、同室内の冷凍冷蔵庫を使用する。
保存性に係る試験は、消費期限を明確にすることを目的とし、
大腸菌群数、一般細菌数の経日変化など必要な項目について調べ
ることとしており、試験は、民間の試験機関に依頼する。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。