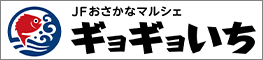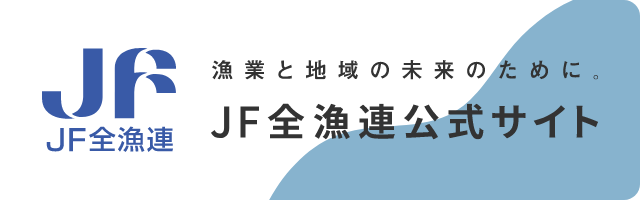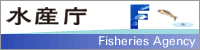浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
1 漁業経営の安定化
① 冷凍加工品の種類の拡大
漁協は、現在の冷凍マダコ(全形・切り身・足のみ・刺身)、
サワラのたたき、アナゴに加え、マダイ等漁獲が比較的まと
まらない魚種についても冷凍加工品を試作し、試験販売を行
う。漁業者は、原料となる漁獲物の漁協への集荷に努める。
② 常温保存できる加工品の開発(缶詰・パウチ等)
漁協は、令和3年度に整備した缶詰製造作業場を活用し、
マダコの加工品の缶詰とマダコの卵の珍味缶詰を試作する。
③ 商標登録を生かしたブランド化推進
漁協は、商標登録済みの「三原やっさタコ」に加え、備後
地域沿岸4市の地魚のブランド「備後フィッシュ」を活用し
た魚の販売を検討する。(備後フィッシュの内、漁協が勧める
魚種を「三原フィッシュ」として推進する。)
④ 新たな販路拡大
漁協は、コロナ禍に対応してECサイトでの販売を行い、
販路を拡大するとともに、小売店等冷蔵冷凍設備が無い店舗
での販売に向け、条件を調査する。
2 新規就業者の育成・確保
① 新規就業者の受け入れ・研修体制の確立
Ⓐ 市の地域おこし協力隊員事業でタコ壺漁師としての就
業をテーマとする隊員を募集し、漁協が短期研修及び中期
研修を行い、新規漁業就業に意欲と適性がある者を選定
し、漁協で長期研修(3年予定)を開始する。
Ⓑ 漁協で研修の状況をSNS等で発信するとともに、研修
生も地域おこしの一環として、研修状況や地域の様子をS
NS等で発信し、新たな就業希望者の発掘の一助とする。
3 西日本豪雨禍等で傷ついた漁場の回復
① 産卵用タコ壺の設置
平成 30 年の西日本豪雨やその後の集中豪雨で土砂が流入
したため、タコが産卵できる岩のくぼみ等が埋まり、産卵場
所が減少している。このため漁協は、市の助成を得て、産卵
用タコ壺を設置し、産卵場所を造成する。
② 藻場礁、増殖場の設置
市は、藻場礁を設置するとともに、増殖場の設置について
場所等を検討する。
4 資源管理の推進
① 種苗放流
漁協は、三原市周辺の漁場環境に適し、定着性が高く、漁
業所得への寄与効果の高い魚種(ヒラメ、カサゴ、キジハタ
等)の種苗(以下「適正種苗」という。)を確保し、それぞれ
の種苗に適した場所に適切な量を丁寧に放流する。
② 釣り具店、遊漁船業者との話し合い
漁協は、タコエギによる負傷被害等を防ぐため、タコエギ
の使用規制について県及び遊漁船業者等と話し合う。
③ マダコ人工産卵実証実験
漁協は、産卵間近なマダコを水槽内に保護し、産卵・孵化
させ、孵化幼生を放流するための実証実験(以下「マダコ孵
化幼生放流実証実験」)を検討する。
5 豊かな里海の魅力発信
① 水産学習への協力
市と漁協は連携して、市内小学校が実施する水産学習に協
力する。
② 食育及び魚食の推進
漁協は、市内小中学校の学校給食で使用する水産物の確保
に努め、市が行う食育推進へ協力をする。
③ イベントへの参加・Webによる情報発信
漁協は、コロナ禍によりイベントの縮小等が予想されるた
め、Webサイト等での発信を強化する。
6 漁港・海岸施設の維持管理
① 能地漁港機能保全計画に基づく維持管理
市は、計画に基づく施設の点検を実施する。
② 能地漁港海岸保全施設機能保全計画に基づく維持管理
市は、計画に基づく施設の点検を実施する。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。