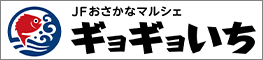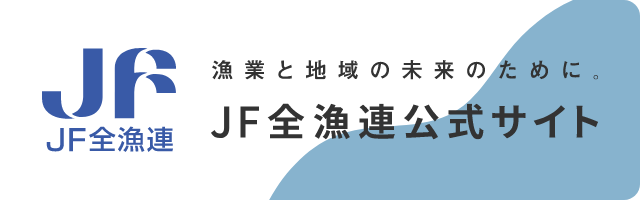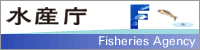浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
①資源管理対策
ア オニオコゼ
漁協は、市場出荷されたオコゼを計測し、18cm以下のものは販売せず
再放流する取組みを継続することにより、資源の増大を図る。
イ ガザミ
漁協は甲幅13cm超の抱卵ガザミを1,000円/kgで買い取ってから再放流
することにより、ガザミの資源拡大を図る。
ウ マダコ
市は、タコ産卵用たこつぼを沈設し、タコの産卵環境を整備する。
さらに産卵期の9月20日~10月10日をたこつぼ禁漁期として、卵を守っ
ている雌タコを保護することにより、タコ資源の増大を図る。
エ アサリ等
水産多面的機能発揮対策事業を活用し、地区毎で形成する漁業者グル
ープは、耕耘による干潟環境の改善、漂流物除去、藻場の再生等に継続
的に取り組み、アサリ等の資源管理を行う。
オ ナマコ・サザエ等
ナマコ、サザエ等の定着性資源については、各地区に採介藻漁業者を
中心に自警グループを組織し、自警船での地先漁場を定期的に監視する
ことによりこれらを保護し、資源管理を行う。
カ 栽培漁業の推進
漁協は漁業者の協力を得て、フグ、カサゴ、カレイ、キジハタ等の種
苗放流の結果を検証しつつ、放流場所の工夫をする等効果的に継続する
とともに、ヨシエビの稚魚の中間育成後の種苗放流を実施し、効果的な
漁獲増を目指す。
また、漁業者からの種苗要望を下松市栽培漁業センターへ伝えること
により新規放流魚の開発に協力する。
②地域主幹漁業の振興対策
ア ハモ延縄
ふぐ延縄の夏場代用漁業として期待されているハモ延縄については、
個人での活漁出荷にとどまっていたが、グループ化を推進し、数量をま
とめて大量出荷することにより、活ハモの販売量を増加させ、価格の向
上を図る。
併せて、魚体を傷つけないように、船上にマットを敷く等取扱手法に
ついて検討し、統一化を図る。
さらに、漁業者を中心とする6次産業化への取り組みを推進し、漁
獲・加工・販売をグループで実施することにより販売価格の向上を図
る。
イ 小型定置網
小型定置網漁業者は、養殖業者と連携し、入網した小サバ、イシダイ
を蓄養し、数を揃えて出荷ロットにすることにより、付加価値向上を図
る。(小サバは5-6月から年末にかけて、イシダイは1年間程度蓄
養)
ウ 販売の多角化
道の駅「ソレーネ周南」で販売する漁獲物の出荷を地区漁業者有志グ
ループによって実施する。(出荷者が価格設定を行ない、販売実績を検
証・分析して販売方法にフィードバックするとともに、小ロット等のた
め市場出荷で値段がつかない水産物の活用を図る)
エ 高付加価値化
漁協は、周南ブランド「徳山ふぐ」、「周防はも」、「周南たこ」に
ついて、地元メディアでの宣伝、祭りや物産展でのPR等を周南市と連
携して行い、周南市内はもとより山口県内での認知度を高めることによ
り高付加価値化を図る。
③漁業経営体等の育成対策
ア ヒジキの利用促進
漁協本店販売部、県の普及員が普及を図っている春の長ヒジキの素干
技術を活用するため、グループ化による共同出荷体制を整え、所得向上
を図る。
イ 未利用アカモクの活用
これまで未利用であったアカモクについて、生産・出荷体制を整備
し、所得向上を図る。
ウ イワガキ・マガキ養殖
ブルーカーボン推進事業を行うため、大島干潟で既に開始している
「カキ養殖による環境保全活動」について、活動範囲の拡大に取り組
む。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。