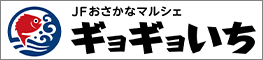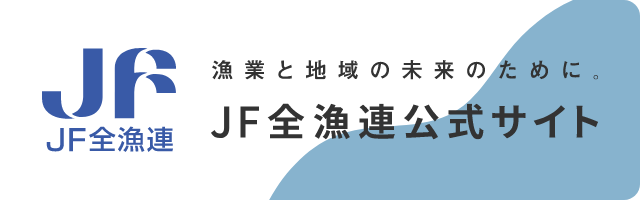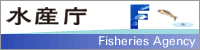浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
①水揚物の高付加価値化、効率的な操業及び水揚げの安定化
・立縄漁業者と統括支所は、清水さばの活魚出荷など、水揚金額の維持に向け
た取組を継続することで、立縄漁業者の収入の安定に努める。
・立縄漁業者は、主要な漁獲対象となっているゴマサバとハガツオについて、
氷焼けや傷などの理由で規格外として扱われることがあることから、統括支
所及び指導所と連携し、漁獲後の船上での取扱い方法や魚倉内での保管方法
などにおける問題点を整理し、漁獲から水揚げまでの鮮度管理方法を決定す
る。
・大型定置網漁業者と一本釣漁業者(ブリ飼付け漁業者)は、主要な漁獲対象
となっているブリについて、以前から魚体筋肉中に血がまわっていることが
仲買人から問題視されていることから、統括支所及び指導所と連携し、船上
血抜きによる高鮮度処理を試験的に行い、仲買人に評価してもらうことで、
ニーズや評価に応じた漁獲後の処理方法を確立する。
・底物一本釣漁業者は、キンメダイの付加価値を高めるため、統括支所及び指
導所と連携し、キンメダイの鮮度管理先進地域における神経締めなどの船上
での魚体処理方法や、底物一本釣漁業者の船の魚倉内水温などの鮮度管理方
法の確立に必要な情報の収集・分析、仲買人などからのニーズ調査を行う。
・曳縄及び一本釣漁業者は、キハダマグロの付加価値を高めるため、統括支所
及び指導所と連携し、キハダマグロの鮮度管理先進地域における神経締めな
どの船上での魚体処理方法や、曳縄及び一本釣漁業者の船の魚倉内水温など
の鮮度管理方法の確立に必要な情報の収集・分析を行う。
・メジカ曳縄漁業者、統括支所及び指導所は、県工業技術センターと連携し、
通常は加工用原魚として扱われるメジカの生食普及を進めるため、メジカの
船上及び水揚げ後の鮮度管理方法や生食の安全性を検証する。
・大型定置網漁業者は、漁獲物の付加価値を高めるため、統括支所及び仲買人
と連携し、神経締めの対象魚種や処理量を拡大し、漁獲物の品質向上に伴う
単価向上及び水揚げ金額の増加を図る。
・大型定置網漁業者は、土佐清水市のふるさと納税の返礼品として、未利用魚
などを活用した鮮魚BOXの出荷の取組を継続しながら、インターネットな
どを通じて、消費者の鮮魚BOXに対する評価や要望を調査する。
・休漁漁場であった定置網漁場(貝ノ川大敷)の操業を再開し、地区全体の水
揚げを増加させる。
・以前から土佐清水市内の立縄漁を始めとする漁業種では、サメによる漁具の
破損や漁獲物の損失などサメ被害に悩まされてきた。そこで当地区の全漁
業者は、市内の下ノ加江地区や窪津地区などの漁業者とも連携しながら、漁
場におけるサメ被害対策としてサメ駆除を実施する。
・「土佐清水市メジカ需給調整対策協議会」において、メジカ曳縄漁業者と加
工業者間の需給のバランス等の課題について定期的に対応策を協議し、課
題解決に向けて取り組む。また、土佐清水市は、当地区で水揚げされるメジ
カの保管及び加工量の増大につなげるため、市が管理する大型冷凍保管施
設、共同加工施設、残渣処理施設の加工業者の利用を促進する。
・統括支所及び全漁業者は、優良衛生品質管理市場認定を取得した清水魚市
場(開設者は統括支所)で水揚げされる全ての漁獲物に対し、同認定基準に
則った衛生品質管理マニュアルに基づく徹底した鮮度管理と衛生管理を行
う。
②漁業者の育成と魅力ある漁村づくり
・統括支所及び大型定置網漁業者は、県が実施している漁業就業総合支援事業
による漁労技術研修や漁船取得支援を積極的に活用し、新規就業者の受け入
れを行う。若い新規就業者を増やすことにより、漁村を活性化し、生産量の
維持及び漁業収入の向上につなげる。
・土佐清水市漁業士連絡協議会などの漁業者団体は、地元水産物を使った魚の
料理教室や、各種イベントでの地元水産物を使った加工品の販売を行うこと
で、地元での食育・魚食普及活動を推進する。
③漁村とその周辺環境の保全及び水産資源の維持・増大
・支所及び全漁業者は、水産業事業継続計画(BCP)に基づく災害対策の推進
及び BCP の普及啓発により、災害発生時の減災や防災、災害発生後の漁業
の継続や復興対策を進める。
・漁業者を中心とした地元住民グループは、サンゴ群落の保全、藻場の再生お
よび磯焼け対策としてのオニヒトデやウニなどの食害生物の駆除や小学校
などでの環境保全の授業実施などにより、生態系の保全、水産資源の維持増
大を図る。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。