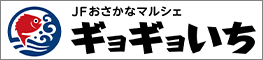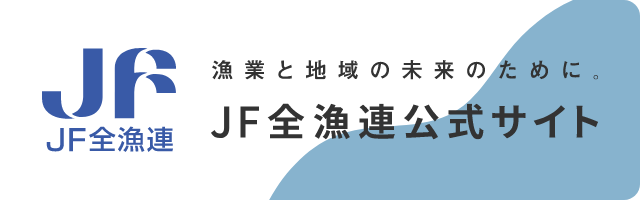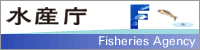浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
▼宇佐地区
【多鈎釣りの振興】
・ウルメは主な用途が塩干物などの加工用であり、一度に大量に漁獲があると
価格が下落する傾向にある。そのため、第1期に引き続き漁業者は自主的に1
日1隻あたりの水揚げ量の上限を定める漁獲制限により、魚価の維持に取り
組む。
・漁業者は漁獲したサバの一部を活かしたまま水揚げする。漁協は、このサバ
を活〆して「宇佐サバ」と名づけ、刺身用としての出荷に取り組む。同時に、
アジについても同様の取り組みを行う。
・漁協は人口が集中している高知市周辺へのアクセスが、他の主要な水揚地に
比べて近いという利点を活かし、これらの高品質な高鮮度ウルメ、宇佐サバ、
活〆アジを高知市及びその周辺の量販店に販売する。
・活かして水揚げされた魚は、市場の水槽で泳がされ、注文に応じて活〆もし
くは活魚として出荷される。しかし、活魚水槽は汲み上げた常温海水を利用し
ているため、海水温が上昇すると魚が斃死するために長期間の仮置きが出来
ず、県内外の業社が要求する一定量の活魚を確保することが難しい。現状需用
を満たす活〆、活魚出荷が出来ておらず、仮に海水温の問題が解決し、業社が
要求する活魚の水揚を確保できれば、活魚出荷の拡大による魚価、収入の向上
及び漁師の活魚需用のある魚種に対する水揚意欲の向上、ひいては水揚量の
増加が望める。6~12月は水揚する多くの魚種について活魚出荷前の仮置
き場として活魚水槽の需要があるが、海水温が好適といえる条件では無い。そ
こで海水温を一定に保ち、6~12月の海水温が上昇する時期であっても十
9
分な活魚を確保し一括して出荷できる体制を整えるため、冷水機の設置を検
討する。
・漁協及び漁業者は、ヒラメの種苗放流を行い、地先海域での水産資源の増大
に取り組む。
・漁協及び漁業者は、中層式ビニール海藻魚礁を設置し、中層に生息するシイ
ラやカツオなどの回遊性魚類の保護育成場としての蝟集基盤の確立と操業の
円滑かつ効率化を図る。
【アサリ漁の復活】
漁協及び漁業者は宇佐地区協議会の構成員として、「かぶせ網」の設置、メ
ンテナンスによるアサリ資源の回復に取り組む。
同協議会は、水産多面的発揮対策事業の終了後、自己資金でアサリ資源の保
護活動を継続し、アサリ資源を活用した地域振興を行うための潮干狩り事業
の実施に向けた体制作りを目的として、アサリの間引き活動のボランティア
募集をOTA(オンライントラベルエージェンシー)を活用して行い、アサリ
資源の増殖を図りつつ、その運営体制のノウハウ蓄積を行う。
天皇州に設置したかぶせ網に大量に付着するカキを初めとした生物がメン
テナンス作業の妨げとなっていることから、付着生物の減少を目的として目
合いの大きいかぶせ網への交換を行う。
※かぶせ網…干潟に網をかぶせ、エイやチヌなどの外敵からアサリの稚貝
を保護する方法
▼深浦地区
【観光釣り筏による地域振興】
漁協が新たに整備した釣筏の利用客数を増やすため、釣り初心者や家族客
を意識した、SNSによるPR活動、釣具店や観光施設でのチラシ配布による
広報活動を継続する
【養殖業の振興】
・ブランド鯛に関する取り組み
乙女会は、薄飼いによる高品質魚の生産と出荷を継続し、併せて販路拡大や
PR活動にも取り組む。
土佐鯛工房は、民間企業と協力して西日本への PR 活動や商談を継続し、販
売尾数の増加を図る。
10
また、新規就業者の確保による生産量の拡充を図る。
・養殖グループによる新たな取り組みの推進
所得向上のため、深浦の養殖漁業者は導入種苗数を 1 人あたり前年比で 200
尾増やす。
必要に応じて、県の養殖協業体の認定も受け、小割の増設による生産尾数の
増加や、販路の拡大を図る。
・漁場環境保全
漁協及び漁業者は、水産試験場の協力を得て赤潮の発生状況を把握すると
ともに、その状況に応じて地元種苗生産会社の協力を得て底質改良剤の散布
することにより、赤潮の発生を抑制する取り組みを継続する。
▼池ノ浦地区
・漁協及び漁業者は、地域独自の禁漁期間の設定や禁漁区や漁獲サイズの制限
※の設定等により、イセエビの資源管理型漁業に取り組む。
また、漁協及び漁業者は密猟者対策のパトロールに取り組む。
※ 池ノ浦地区では、180g 以下のイセエビ(調整規則では 13cm、概ね 100g 以
下)の採捕を禁じており、このサイズのイセエビが漁獲された場合は、漁協が
買い取った上で放流することにより、資源の維持に努めている。
・イセエビ以外での収入増を目的として、ヒオウギガイの放流と吊り籠による
垂下に取り組む。また、平成 31 年2月に放流した 2,000 個の稚貝(内 200 個
の稚貝を吊り籠に入れて垂下)のサイズや状態を観察しつつ令和2年度まで
放流を行う。
・池ノ浦地区の漁業者で組織する池ノ浦伊勢えび組合は、漁協と連携して行う
個人配送や須崎市ふるさと納税の返礼としての発送に取り組む。また、リピー
ターの安定的な確保に資するため、ホームページによる情報発信と情報の充
実を図る。
▼久通地区
・地域独自の禁漁期間の設定や禁漁区の設定等により、イセエビの資源管理型
漁業に取り組む。
11
▼上ノ加江地区
【体験型観光漁業の推進】
・新規顧客の獲得
上ノ加江支所は県地産外商公社が運営する高知県産品のアンテナショップ
「まるごと高知」での情報発信、県主催の観光事業(龍馬パスポートなど)の
登録を継続しつつ、新たな観光推進事業への登録により、同支所が実施する体
験漁業の認知度を向上させていく。
体験漁業の営業活動を学校、企業、旅行会社、ホテル・旅館等を対象に実施
し、営業先の客層のニーズに合わせた提案を行う。
中土佐町のふるさと納税の返礼品として「漁業体験ペアチケット」の提供も
継続する。
漁協の HP、登録している観光ポータルサイトの内容充実、新たなサイトへ
の新規登録を引き続き行い、フェイスブックやツイッターなどによる、リアル
タイムでの情報発信にも力を入れる。
利用客の紹介によって新規で参加した人に対する特典や、体験参加者は鮮
魚を浜値で購入できる等、魅力的な特典を設ける。
・リピーター顧客の獲得
顧客リストに基づいて、体験参加への礼状や時候の挨拶ハガキ、地域内で開
催されるイベント案内等を送付する。
体験内容についてのアンケートを引き続き実施し、新たなメニューの考案、
開発により、繰り返し参加しても飽きない構成にするとともに、結果を漁業者
にもフィードバックして共有することで、体験漁業の品質向上を図る。
また、リピート参加の利用客には次回の参加料割引チケットを渡すなど、さ
らに特典を充実させる。
・体験漁業の充実
漁協と漁業者は、雨天時に出漁できない場合や、利用客が乗船を望まない場
合にも対応できるよう、それに代わるメニューを準備していくことで体験漁
業の更なる充実を図る。
また、講師として参加する漁業者間のサービスの均質化と更なる向上を図
るため、講師が一堂に会する場を設けるなどして情報交換に努める。
さらに、学校、PTA、児童クラブ等に対しては、学校教育と関連した食害生
物駆除及び駆除した魚の調理活動等を行い、漁業体験の機会を提供するとと
もに体験内容の充実を図る。
12
▼矢井賀地区
【観光釣り筏による地域振興】
観光釣り筏のPRのため、インターネットでの情報発信の体制を活用し、中
土佐町や観光会社との連携を深めながら、自らも情報発信に取り組み、リピー
ター及び新規顧客の確保に努める。
また、令和元年度に台風被害を受けた釣り筏を取組1,2年目に再設置し、
収容力の向上による集客増を図る。
▼志和地区
・資源保護の取り組み
地域独自の禁漁期間の設定や禁漁区の設定等により、イセエビの資源管理
型漁業に取り組む。
・資源増殖の取り組み
間伐材を利用した稚エビ魚礁の設置を、効果を検証しながら継続して行い、
イセエビ資源の維持増大を図る。
▼各地区共通
【漁業者の育成】
・漁協は、新規漁業就業希望者を漁業研修生として積極的に受け入れ、担い手
の育成を推進し、将来的な水揚量の増加を図る。
・漁業者及び漁協は漁業研修生と定期的に面談等を行い、漁業研修生が漁業者
として定着できるよう支援する。
・漁協及び漁業者は磯焼けの原因となる有害なウニや魚の駆除を行い、藻場造
成に取り組む。(主に宇佐、池ノ浦、志和地区)
・産地の PR 活動
漁業者は、地元で開催される地域イベントに参画し、産地としての知名度向
上と消費の拡大に努める。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。