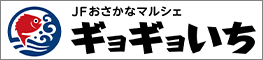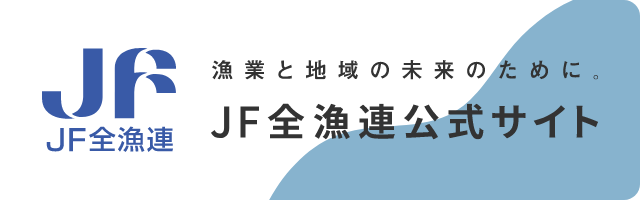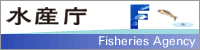浜プランの取組地区数※2025年3月末時点
5 6 3 地区 ※2025年3月末時点
(1)強い経営体の育成
全漁業者及び漁協は、養殖共済や施設共済の加入状況と内容を
改めて確認しながら、見直し等の必要性について検討し、災害時
等における収入の安定化を図る。
個人での事業継続は多額の資金が必要となることから、漁業者
は協業化や分業などにより効率的な生産を行うとともに、漁協は
機器更新のための積立金計画や経営管理指導を行い、漁業者の経
営力強化や収入の安定化を図る。
漁協は浜ごとの栄養塩状況の確認や生育状況、色調等の調査を
行い、当該情報を逐一生産者へ伝達することとし、漁業者はその
結果を受けて、摘採時期の調整を行うことで、ノリの品質確保に
努め収入の安定化を図る。
(2)海洋環境変化への対応
① 水質調査の実施
地域により養殖漁場内の栄養塩濃度に差があることから、漁協
は浜ごとに行う水質調査を通じて、漁業者に対して最適な摘採時
期にかかる情報提供を行う。併せて、必要に応じ病障害を未然防
止するための早期の摘採を促すことにより、漁業者の生産及び収
入の安定化を図る。
② 環境に適応したのり生産体制の構築
高海水温に伴う育苗時期の遅れから外洋への張り込みが遅れて
しまうことを防ぐため、漁協は定期的な水温把握を通じて、漁業
者に対して情報提供を行うとともに、水温が高めで推移した状態
での育苗や早期の刈取りを可能とするため、県水産技術総合セン
ター等の研究機関と検討・協議を行いつつ、本県海域に適した種
苗の開発・導入を図る。
③ 病障害の対応
赤ぐされ病や、近年仙台湾全域にバリカン症状が発生している
ことから、漁業者及び漁協は研究機関と連携し、漁場利用計画及
び適正養殖可能数量に基づき、筏の間隔を確保することで潮通し
を良くし栄養塩が均一に供給されるよう努める。
(3)養殖生産物の品質確保
① 漁場の有効活用・適正利用
全漁業者は、筏の管理や海底清掃などの協業化を進めるととも
に、漁場環境の把握に努めるために調査とデータ収集を実施し、
漁場利用計画において科学的根拠に基づく適正養殖可能数量を定
め、密殖を防ぎ、品質向上を図る。
② 未侵入疾病への対応
漁協は、適正密度での生産を指導する。漁業者は県のガイドラ
イン等を遵守するとともに、県試験研究機関等の指導を踏まえた
適切な疾病・斃死対策に取り組むことで収入の安定化を図る。
③ 生産技術の改善・改良
ほたてがい養殖における地先種苗活用など漁場環境変化に対応
した生産技術の改良や市場ニーズ等の分析を進め、高品質化及び
安定生産を図る。
④ ぎんざけ種卵・種苗の安定的確保
国内からの種卵供給は北海道に限定され、年々種卵確保が難し
くなりつつあることから、漁業者及び漁協は、種卵生産者から購
入する親魚の管理について以下の取組みを行う。
a) 漁協は、近親交配による奇形魚発生を回避するため、県内水
面水産試験場から定期的に雄親を調達し、種卵供給業者に提
供する。
b) 漁協は、種苗の安定的な導入とリスク分散のため、地下水を
活用したぎんざけ親魚の独自養成と採卵技術の導入に向け検
討を始める。
(4)養殖生産物の安全確保
① 異物混入防止の徹底
漁業者各々が目視検査を徹底するとともに、漁協は、漁期前の
部会や研修会等で漁業者へ異物混入防止について周知・啓発す
る。
② ノロウイルス等の衛生対策及び貝毒等検査体制の強化
全漁業者及び漁協は、ノロウイルス・貝毒等の検査体制を強化
するとともに、研修会等を通じ衛生管理等の知識の向上を図る。
また、新たなノロウイルス検査法として期待される感染性推定遺
伝子検査法について過去に県が実施した事業成果等を踏まえ、そ
の有効性や現検査法からの移行による効果等について協議する。
③ 貝毒プランクトン調査及び貝毒等検査体制の強化
二枚貝生産者及び漁協は、貝毒等の検査頻度向上など、検査体
制を強化するとともに、ほたて流通振興協議会等と連携し、研修
会等を通じ衛生管理等の知識の向上を図る。
また、貝毒プランクトン調査について県の試験研究機関と協力
しながら採取定点やサンプル数等を改めて検討し、漁業者等へよ
り有効性のある情報の発信ができるよう努める。
④ ほたてがい加工製品の販売力強化
「ほたて貝取扱い及び加工処理要領」の内容を遵守し、安全性
の担保された加工品の安定的な出荷を図り、ほたて養殖業者の経
営安定化に努める。
⑤ 放射性物質検査
風評等払拭のため、関係機関と連携して放射性物質検査を確実
に行うとともに、安全性が確認された商品であることを、HP等
を通じて周知する。
⑥ のり漁場における適切な活性処理剤の使用
活性処理剤使用取扱要領を遵守し、活性処理剤の使用後5日以
上経過した後に摘採を行う。漁協は、漁業者が同要領の下で採
苗、育苗の漁場環境を踏まえつつ同処理剤を適切に使用すること
を徹底するべく、必要に応じ漁業者に対して研修会等を開催す
る。
(5)販路の回復・拡大
全漁業者及び漁協は、関係機関と連携を図りながら、買受人や
流通業界とも協力し、下記取組により販路の回復、拡大を図る。
① 効果的なPR活動や販売の実施
地元買受人等と連携し各地域で開催される催事等に積極的に参
加するとともに、物産施設等を活用した販売を拡大する。また、
地域でのPR及び販売活動を推進するべく、消費者ニーズの把握
に努めつつ、加工製品等の種類の充実を図る。
② 消費者ニーズに応じた流通体制の構築
前プランで、新たな流通形態の構築と販路拡大を目指し取り組
んだ殻付かきのインターネット取引については、利用者増加につ
ながっていない現状を踏まえ、改めて実施内容を検討する。
③ 春季以降の生食用かき出荷数量増加
県の「生食用かきの取扱いに関する指導指針」の一部改正によ
り正式に出荷可能となる8月の生食用かきの安全性確保に向けて
衛生対策の充実を図りながら、春先の身入りのよい生食用かきの
魅力を発信するとともに、同期間の出荷数量増加につなげる方策
について検討を始める。
④ 輸出に向けた取組
福島第一原発処理水の海洋放出に伴う風評等の影響により、韓
国、中国、香港など一部の国・地域では禁輸措置を講じており、
その対応が課題となっている。震災前に韓国向け輸出が過半数を
占めていたほやをはじめ、これらの措置の影響を受けている水産
物について、県等と連携し、商談会等を通した代替販路の拡大等
に引き続き取り組む。また、禁輸措置を講じている国・地域への
輸出再開に向け、関係機関への積極的な働きかけを継続する。
| 付加価値向上 | 生産・流通 | 外食・観光 | 消費拡大 | 計 | 参考 各地の浜プラン | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 32 | 16 | 7 | 33 | 北海道 | |
| 東北地区 | 62 | 31 | 3 | 22 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県 山形県、福島県 | |
| 関東地区 | 70 | 40 | 16 | 13 | 茨城県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
| 北陸地区 | 24 | 12 | 4 | 19 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 | |
| 東海地区 | 23 | 19 | 13 | 14 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 | |
| 近畿地区 | 30 | 11 | 10 | 33 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県(日本海側)、 兵庫県(瀬戸内海側)、和歌山県 | |
| 中国地区 | 32 | 10 | 15 | 44 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | |
| 四国地区 | 40 | 53 | 5 | 75 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 | |
| 九州・沖縄地区 | 73 | 59 | 41 | 67 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 | |
| 計 |
「浜の活力再生プラン」(通称「浜プラン」)は、2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取組です。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取組計画を「浜プラン」と呼びます。
浜プランは、漁業者や市町村を中心に組織された「地域水産業再生委員会」が、課題・計画・目標を見据えて立案します。
その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入を向上させる取組、コストを削減する取組など、多種多様な具体的なプランが実践されています。
浜ごとに策定される浜プラン。浜の数だけ課題があり、取組が行われています。大きくは以下のような取組が全国の浜で取組まれています。
<収入向上の取組>
高鮮度出荷・加工品開発、直販・輸出など
<コスト削減の取組>
省エネ機器の導入・協業化・船底清掃の取組実施など
浜プランは、「地域活性化のための処方箋」です。
各地域が抱える課題に対し、漁業者と市町村がタッグを組んで自ら考えた解決策を実践することに、浜プランの本質があります。漁業や水産業の改革によって地域全体を元気にすること、「地域創生」に貢献することが、それぞれの浜プランの役割です。